 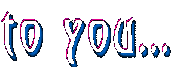
prologue
その日の放課後、教卓の上は私の居城だった。
ほら、時代劇とかでよくあるじゃない?
殿様が小高いところで城下を見下ろすようなシーンが。あんな感じに近い。
此処は、私の場所。
誰にも侵すことの出来ない領域。
いつもは難解な公式や数え切れない年号で埋め尽くされた黒板は、嵐が去った後のようにすっきりとしていて。
それらに頭を悩ませ、ノートと黒板、教師の顔とを順に見遣る生徒の姿もない。
「やぁっ―――な、何っ、何するのっ……」
いや。正確に言うと、生徒の姿それ自体は、ある。
男が三人。女が一人。そして私。計五人。有名大学への進学率において名高い、この私立成陵高校の生徒であることには間違いない。
ただ、男共の視線はチョークで書かれては消えていく方程式を追うのではなく、恐怖に怯える女の身体を纏わり付く様に厭らしく這い、
女も授業中に見られるような、ただ回答を述べる涼しげな声音とは程遠い、哀れみを誘うような悲鳴を上げていた。
「勿論、退会の儀式だけど?」
だからって「可哀想」なんて風に許してなんかやらない。
間髪いれずに答えてやったら、それをゲームの始まりだと思ったらしい3人が、一斉に女に詰め寄った。
一人は女の背後に回り、両腕をがっちりと掴んで羽交い絞めにする。
もう一人は暴れる女を一緒に押さえつけながら、素早く且つ制服が傷まない様に彼女の肢体を晒していく。
最後の一人はブレザーからデジカメを取り出して、女にピントを合わせた。
「も、やぁっ……やなのっ、もう嫌ぁああっ!!」
「ハイハイ、大人しくして?直ぐ済むからさぁ」
男にしては長めで派手な茶髪をさらりと揺らしながら、女の前で慣れた風に服や下着をずらしている三宅が笑った。
深緑のブレザーの下は白いシャツ。そこから覗く白とピンクの水玉のブラはいかにも高校生っぽいデザイン。
私から見ればちょっと甘すぎる気もするけど。
「誰か、助けてぇええ!」
黙って大人しくしている筈のない女は、渾身の力をこめて抵抗する。
後ろで動きを封じている男の眼鏡に肘があたり、それがずれると、眼鏡の男――鳴沢が舌打ちをする。
「そんな元気にしてるとヤっちゃうよ?」
「―――………っ」
鳴沢は冗談交じりに紡いだみたいだけれど、目が笑ってない。
この状況で唯一、全てを見渡すことができる殿様の私には解っているし、知っている。
受験生ということもあり、日々勉強を強いられている彼らは、欲求不満の固まりだ。
こんなおいしいチャンスに遭遇しておいて、易々と逃したくはないのだろう。
けれど、私が殿様ならば彼らは配下。私の命令は絶対であり、「そうしろ」と言った以上のことをしてはならない。
そういう暗黙のルールが存在するのだから、鳴沢や他の二人も衝動を抑えるのに余裕はない。きっと。
いつの間にやら下着の奥に隠れていた乳房や恥丘を晒されてしまった女は、ボロボロと大粒の涙を零している。
あーあ。ちょっと剥かれたくらいで泣くなよ。
つい最近までは、もっと怪しい目つきしたジジイにそれ、見せ付けてたんだろうに。
程よく突き出たバストにきゅっと締まったウエスト、そして柔らかな曲線を描くヒップは下品ではない程度に豊か。
高校生のボディラインにしては合格どころか優良点を付けたい。
顔だって決して悪くないと思うし、できれば、制服というオマケを取り払って鑑賞したいくらいだ。
しかし、制服……ねぇ。
ある程度年齢を重ねた大人というのは不思議な生き物だ。制服というオプションにオーバーな程の価値を見出しているんだから。
なんて、別に今はどうでもいいか。
「うわ、エロいアングル。襲われてるってカンジ」
キヒヒ、とか下劣な笑いを洩らしながら、それとは対照的な奥ゆかしい顔立ちの神藤が言った。
三人の中で一番背が低い彼は、ちょっと上を仰ぐような形で女の姿をデータに収めていく。
たいたフラッシュが火花みたいに、チカチカ、視界に弾けた。
「ひ、どっ………撮ら…ないでっ――……」
「酷くなんてないよ。コレで許してやろうっていうんだから、感謝して貰わなきゃ」
女の口から嗚咽交じりに零れた言葉が心外で、肩を竦める。温かい救済措置だっていうのにさ。
「コレでぜーんぶ無かったことにしてあげるって言ってんの。解る?」
「だからさ、君が援交してたってこと、忘れてやるって言ってるんだよ」
不意に抵抗の力を緩めた女の様子に、小さく息を吐いて鳴沢が呟く。
裏切り者のアンタを、たった数枚の写真で解放してあげるんだよ。
なんて優しいんだろね、私たち。
「ほ、ホント……? 無かったことに、してくれる……?」
さっきまで激しく暴れていたのが嘘みたいに、女が問う。
やっぱ最近の女子高生ってのはゲンキンだ。あぁ、私もそうだったっけ。
今までの子たちと全く同じ反応を見てしまえば、思わず苦笑が零れる。
「ホントホント。その代わり『Camellia』のこと、誰かに喋ったらどうなるかわかってるよねぇ」
「わ、わかってるよ、誰にも言ったりしないっ!! 黙ってるからっ、だからっ」
「OK、それなら交渉成立。皆、解放してやって」
私からの号令が掛かると、三人は各々彼女から離れていく。
女は涙を拭うよりも先に乱れた衣服を整えて、誰かと競争でもしているのかと思うようなスピードで教室を出て行った。
あまりに必死だったと見えて、高校指定のスクールバッグがぽつんと後に残る。
「忘れていったみたいだな」
手持ち無沙汰なのか、制服のズボンのポケットに手を突っ込んで三宅が荷物に視線を落とした。
「あぁ……じゃあ僕が後で届けるよ」
応えたのは鳴沢。
神藤はたった今撮った画像を確認するのに夢中で、聞こえてすらいないようだった。
ひょっとしたら、過去に同じようなシチュエーションで撮った写真の数々をもう一度閲覧しているのかもしれない。
生身の女よりも画像の方が良いだなんて、つくづく変わった奴だ。
「あはは、流石クラス委員の鳴沢くん。優しいんだからぁ」
「そういう水上だってクラス委員だろう。大人しそうな顔して、お前も怖いヤツだよな」
明らかな皮肉。鳴沢が私へと、同じそれを返した。
「怖い? こんなに真面目で優等生な私が?」
私はわざと唇を吊り上げるみたいな、歪な笑みを浮かべて言った。
鳴沢も三宅も、デジカメに心を奪われていた神藤さえも今度は一緒になって笑った。
ちょっと調子に乗って虐めすぎたかな。本当は、もっと穏便に済ませてやってもよかったんだけど、
被害者面な趣旨をほざいてたもんだから、つい荒っぽい解決法になってしまった。
ああいう女ってイラっとするんだもん。仕方ないよね。
でもま、一応、フォローしといてやるか。
ブレザーのポケットから携帯電話を取り出すと、両手を使ってさっさと文章を打ってしまう。
勿論、さっきのあの女宛てだ。
――――――――――――
宛て先 : 【D】村井彩夏
件名 : From Camellia
――――――――――――
本文 :
今日までご苦労様。
貴女が他言しない限り、
『camellia』での出来事は
全て私たちと貴女だけの
秘密。
だから安心してね。
それと、良い子がいたら
紹介を宜しく。
では、彼氏とお幸せに?
―――――END―――――
「さっきの子?」
「んー」
鳴沢に訊ねられて、送信ボタンを押しながら頷く。
「あの子、いっぱい稼げそうだったんだけどなー」
残念そうな声を出す三宅。
「彼氏のために援交止めるなんて、微笑ましいじゃない」
その気持ちはわからなくもない――とは、三人には言わなかった。
液晶画面に浮かぶ『sending…』の文字が消えるのを待ってから、静かに、携帯電話を閉じた。
今日の仕事は、これでおしまい。
|